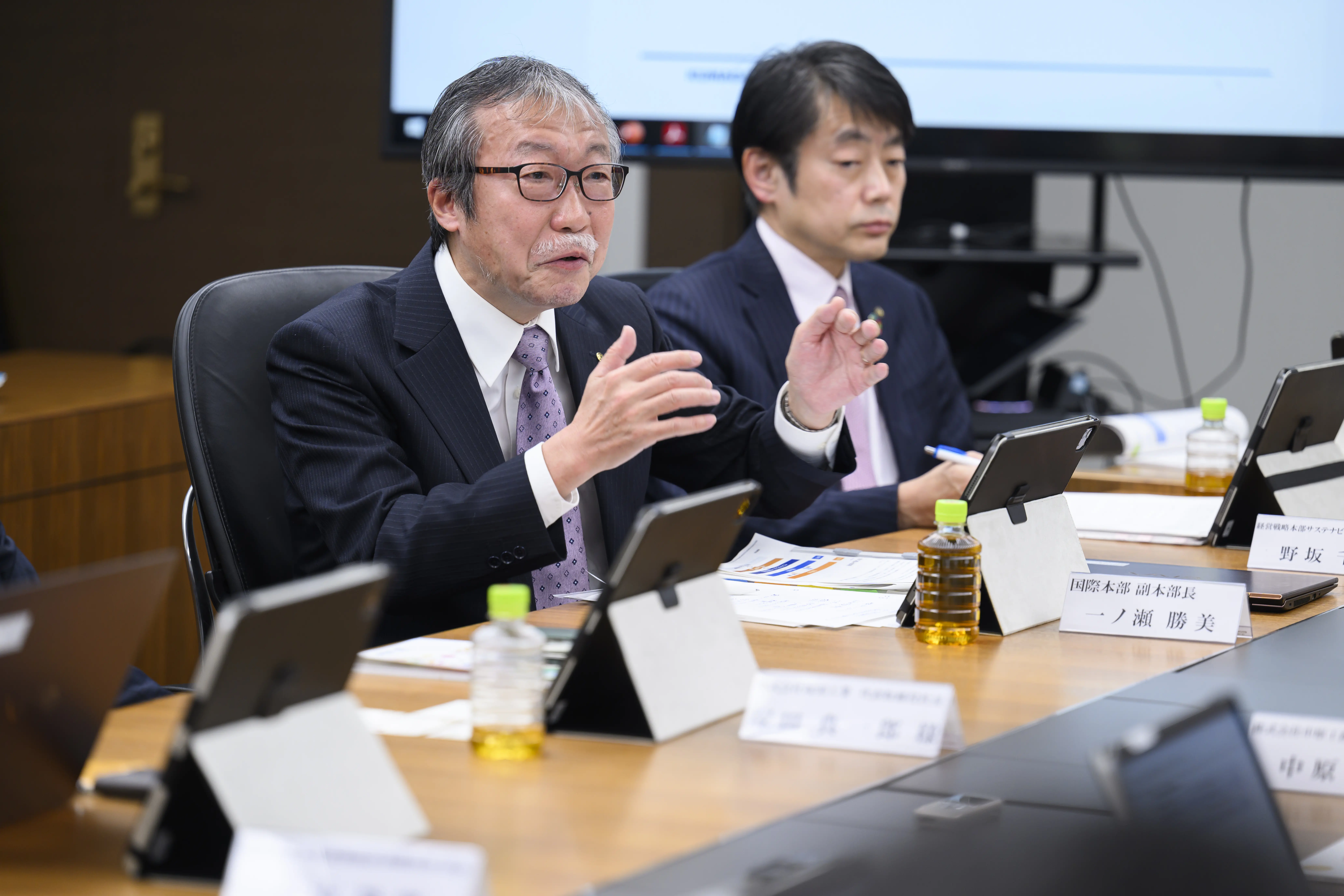熊栄協力会人権意見交換会
熊栄協力会人権意見交換会 参加者(写真前列左から)

| 弁護士 / 元経済産業省 ビジネス・人権政策調整室 室長補佐 | 塚田 智宏 氏 |
|---|---|
| 株式会社熊谷組 土木事業本部 副本部⾧ | 中村 圭 |
| 株式会社熊谷組 経営戦略本部 本部⾧ | 清水 直博 |
| 共栄機械工事株式会社 代表取締役社長 | 齋藤 隆 氏 |
| 笹島建設株式会社 代表取締役社長 | 笹島 義久 氏 |
| 新妻鋼業株式会社 代表取締役社長 | 新妻 尚祐 氏 |
| 株式会社熊谷組 建築事業本部 建築統括部 購買部 部⾧ | 小山 隆則 |
| 株式会社熊谷組 安全本部 協力会連携推進部 部長 | 籔 理一郎 |
| 株式会社熊谷組 建築事業本部 副本部長 | 下川 智男 |
| 株式会社熊谷組 管理本部 人事部 部長 | 池内 浩 |
| 薩摩建設株式会社 代表取締役社長 | 山﨑 哲也 氏 |
| 株式会社熊谷組 国際本部 副本部長 | 一ノ瀬 勝美 |
| 株式会社中原工務店 代表取締役社長 | 中原 勧 氏 |
| 株式会社熊谷組 経営戦略本部 サステナビリティ推進部 部長 | 野坂 千博 |
| 株式会社塚田工業 代表取締役社長 | 塚田 真一郎 氏 |
| 株式会社HEXEL Works 執行役員東京第一支店長 | 清水 光茂 氏 |
- 役職は2025年1月時点のものです。
現場での人権への意識を高め、サプライチェーン全体の公平性を目指す
熊谷組では、2022年度、「熊谷組グループ人権方針」を策定し、その実効性を高めるためにさまざまな施策を進めています。2023年度は当社事業において特にリスクの高い人権課題を優先的に取り組むべき重点課題として特定しました。その中でも建設業における特徴的な課題である外国人労働者に関わる取組みをテーマとして、熊谷組の協力会社組織である「熊栄協力会」との意見交換会を実施しました。始めに、当社の人権方針専門部会の部会長である清水が当社における取組みの概要を紹介。その後、オブザーバーである弁護士の塚田智宏氏を交え、熊栄協力会と熊谷組を代表するメンバーが意見を交わしました。
[外国人労働者の受け入れ状況]
建築の現場では3分の1近くが外国人労働者の場合も
清水(熊谷組)
今日は人権の中でも、特に外国人労働者に関わる取組みに焦点を絞って、皆さんと率直な意見を交わしたいと思っています。まずは各社における外国人労働者の受け入れ状況をお聞かせください。
山﨑
当社では17名が働いています。2017年に技能実習生として受け入れ、早いものでもう7年になります。現在は17名のうち4名が特定技能となっています。
塚田
当社が受け入れを始めたのは2007年です。現在は24名。内訳は技能実習生が13名、特定技能者が11名です。
齋藤
当社ではまだ外国人を受け入れたことはありませんが、現在、活動を進めています。
笹島
おそらく山﨑さんや塚田さんの建築分野と、私や齋藤さんの土木分野では状況も違うのでしょうね。土木の現場では特殊な技能が求められることも多いため、まだ比較的少ないのだと思います。当社では、協力会社を含め8名が働いています。
中原
当社も土木分野ですが、現在は2名です。ちなみに協力会社を含めると15名の外国人労働者が働いています。
清水
当社は電気設備を専門おり、土木と同様で分野的に少なく、総合職の採用枠で1名雇用しています。また、現在、フィリピンで新卒採用を進めています。
新妻
当社は、鉄筋専門の工事業者として建築・土木の両分野に関わっています。外国人労働者については1999年から受け入れており、これまで70名以上が就業しています。国籍も多彩で、現在8か国の外国人が在籍しています。また、清水さんの会社((株)HEXEL Works)と同じように、インドネシアで大卒社員の採用も進めています。
清水(熊谷組)
新妻さん、鉄筋工事における外国人の割合はどのような状況なのですか?
新妻
おそらく皆さんの想像以上だと思います。全国鉄筋工事業協会によると全国で約4万人いる鉄筋工のうち、すでに1万人が外国人だそうです。2025年1月の東京都での技能検定では受検者の3分の1以上が外国人です。
塚田
その割合は、建築の現場全体にいえることだと思います。先日、都内のマンション建築現場に行ったところ、技術者の45%が外国人ということでした。
中原
一方、土木の現場ではまだ1割くらいでしょうか。
新妻
現実ではもうそこまで来てしまっているわけですよね。建設経済研究所が「2030年に技能労働者の不足が顕在化する」というレポートを出していますが、私はその危機がもっと早く到来するのではないかと考えています。
清水(熊谷組)
このような生の声を聞くと、非常に切実な問題であると実感します。
[人権に関わる具体的な取組み]
「外国人だから」という意識を持っていてはダメ
清水(熊谷組)
外国人労働者の人権について具体的な取組みを教えてください。
清水
当社では外国人労働者はまだ1名ですが、日本人と同じような感覚で接しています。彼は日本語が堪能で、すでに電気関係の資格も取得しています。このような教育研修についても積極的に支援しています。
中原
当社も同ように、国籍などに関係なく、日本人社員と同じように定期的に社内面談を行い、社員会での旅行などにも積極的に参加してもらっています。
資格についても同様で、すでに型枠関連の資格を持っており、現在は溶接関連の勉強をしています。将来的には自動車の免許も取りたいと意欲的で、その足がかりとして原付免許の取得を支援しているところです。
新妻
私も常々心がけているのは、「外国人だから」という意識を持たないこと。処遇も教育も、あるいは考え方や個性などについても各人を尊重するようにしています。過去には宗教の違いなどを理解できずにトラブルになることもありましたが、私たちの考え方や文化を一方的に押しつけないようにすることで関係もよくなったと感じています。
実際、当社ではこれまで70名以上を受け入れてきましたが、いわゆる「失踪」という形で辞めた人はわずか2名です。
外国人労働者の「失踪」が話題になりますが、こういった会社は基本的に人権に対する意識が低く、外国人ばかりでなく日本人への対応にも問題があるのではないでしょうか。人権のことをしっかり考えない会社は、これからは事業の継続そのものが難しくなっていくと考えています。
笹島
建設業界には多重下請けという構造があり、人権において3・4次あたりの下請けまでになると目が行き届かないという課題があるように思います。
野坂(熊谷組)
欧米では、労働者の人権について、サプライチェーン全体で捉える動きが強まっています。これからは私たちも、そのような視野で取り組んでいくべきだと考えています。
[熊谷組の取組みについて]
国籍に関係なく、一緒に働く仲間として受け入れる
塚田
外国人労働者への対応については、熊谷組は積極的だと感じています。当社が受け入れていた技能実習生の現場入場についても、熊谷組は早くから協力的でした。
中原
外国人とのコミュニケーションでは言葉の壁がありますが、最近はスマホの翻訳アプリなどを使うことである程度解消できるようになってきましたよね。当社では、このような機能に注目して、外国人労働者に対してスマホの購入代金の一部を支援しています。
熊谷組の社員はツールの活用にも積極的で、当社の外国人労働者たちに対して丁寧に意思の疎通をはかってくれているように思います。
中村(熊谷組)
確かにスマホのアプリは便利ですね。熊谷組の社員たちも現場で欧米のエンジニアなどとやりとりする時に活用しているようです。
山﨑
当社には特定技能になって長く働いている外国人がいます。彼は熊谷組の現場の所長や主任にとても目をかけてもらっていて、次の現場の指名がくるほど。熊谷組では、国籍に関係なく、一緒に働く仲間として受け入れてもらっているように感じます。
ベストプラクティスを共有し水平展開してほしい
清水(熊谷組)
熊谷組への提案などもぜひお聞かせください。
塚田
熊谷組では、5か国語の冊子を作るなど、安全教育にも積極的ですが、個々の現場を見るとまだまだ取り組むべきことは多いと感じています。
山﨑
先日、熊谷組と熊栄協力会が合同で行っている安全パトロールを首都圏支部で実施した際、外国人労働者の安全教育をさらに強化していこうという話になりました。そこで現在、現場での新規入場者教育や各種教育を、翻訳ツールを使って多言語で行う取組みを始めています。
齋藤
そういう取組みは、熊栄協力会の活動としてどんどん全国へと水平展開していくべきでしょうね。
中原
山﨑さん、首都圏支部では熊谷組と共同で職長教育も始めているという話を聞いていますが。
山﨑
ええ。その背景の一つに、永住権が得られる特定技能2号を取得するためには、職長の実務経験が必要であり、そのためには職長教育が必要となります。長く日本で働きたいという外国人労働者の意欲を応援する取組みでもあるのです。
新妻
他のゼネコンでは外国人技能実習生を対象とした表彰制度などを検討しているところもあるようです。
山﨑
熊谷組でも、現場レベルで実施しているところがあります。それらをまとめて全社的に行うようにすると、現場のエンゲージメントが高まると思います。
清水
熊栄協力会での水平展開の話が出ましたが、今回のような情報交換の場をこれからも積極的に設けてもらえると、参加企業にとっても役立つと思います。

[これからの課題1]
外国人だけでなく、日本人社員向けの人権教育も大切
清水(熊谷組) さらに議論を深めて、これからの課題について意見を交わしたいと思います。
中原
難しいのは、やはり現場での教育だと感じています。資格取得の勉強は机上でもできますが、職人としての技術や安全への意識など現場でなければ学べないことも多い。当社ではなるべく経験豊富な日本人社員と組ませるなど気を配っています。こうして身につけた技術や知識を、いつの日かそれぞれの国に持ち帰って活躍してもらえたら嬉しいですよね。
もう一つ人権として日頃から意識しなければならないのは、考え方や文化の違い。処遇や福利厚生などについて、時には日本人の常識では思いつかないような要望を出されることもあります。その違いもしっかり受け止めて一緒に考えています。
一ノ瀬(熊谷組)
自分たちでは配慮しているようでも、ついつい無意識のうちに偏った見方をしている場合もありますよね。
野坂(熊谷組)
そういうことを考えると、外国人ばかりでなく、日本人社員に対する人権の教育も大切になってくると思います。
笹島
人権ということでは、処遇も大切ですが、だからといって勤務に関わる衣食住をトレードオフするような考え方は間違っていると思います。
中村(熊谷組)
土木の現場は町から遠く、通勤に時間がかかり、外国人労働者も宿舎で長期間生活するようなこともあります。
笹島
熊谷組はそうした環境もよく整備されていると思います。さらに現場レベルで徹底できるようにたえず本社から発信し続けてほしいと思います。
[これからの課題2]
サプライチェーン全体での処遇改善こそが早急な課題
塚田
今後の課題をあげるとするなら、これは人権とも密接に関わるのですが、やはり賃金、処遇に尽きると思います。建設業界でも労務費は急速に上昇しており、今後は制度の変更などに伴って業界の中でも外国人労働者の流動性も高まっていきます。冒頭に話題に出たように、今や建設の現場は外国人労働者なくしては成り立たない。優秀な人財を確保するためにも、賃金をはじめ処遇の改善こそが早急に考えるべき課題だと考えています。
新妻
塚田さんの言うとおり、これは熊谷組だけでなく、建設業界全体で考えるべき課題です。外国人労働者はもはや国際市場であり、他の国々との競争にもなっています。このような状況のなか、彼らにとって働きがいのある環境を整えていくためには、やはり処遇の問題が鍵を握ります。そのためには業界ばかりでなく発注元も含めた意識改革が必要です。
清水(熊谷組)
いずれもとても重い言葉だと思います。
野坂(熊谷組)
先ほど話したサプライチェーン全体での取組みに加え、積極的な情報開示もこれからの重要なテーマであると考えています。各社が人権に関する方針や取組みなどの情報を発信し続けることによって、発注元および建設業界全体の人権意識も高まってくるのではないでしょうか。
池内(熊谷組)
人権の取組みにおいて、安全をはじめとする教育が非常に重要です。しかし、それが行きすぎるとパワーハラスメントになってしまう懸念もあります。そのため、このバランスに配慮することがとても大切です。
下川(熊谷組)
現場での安全管理には日本語によるコミュニケーション能力が深く関わってきます。新規入場者教育などで日本語能力を見極める仕組みが必要になると考えています。
籔(熊谷組)
今後は熊栄協力会とアイデアを出し合いながら、ホームページでの発信をはじめ水平展開のための取組みを積極的に進めていきたいと考えています。
一ノ瀬(熊谷組)
今日皆さんの話を聞いて実感したのは、人権の取組みはもはや当たり前のことであり、その先にある、建設業を選んでもらうためのより働きやすい環境や、やりがい等に注力すべきであると実感しています。
中村(熊谷組)
それは外国人ばかりでなく、日本人に対しても同じこと。誰もがいつまでも一緒に働いていける環境づくりが大事だと思います。
小山(熊谷組)
時代を超えて、建設は「人がつくる」仕事なのですよね。改めて熊谷組と熊栄協力会が一体となった取組みの大切さを認識しました。
清水(熊谷組)
私が今日改めて感じたのは、こうして膝をつき合わせて意見を交わすことによって伝え合えることがたくさんあるということです。人権の取組みは、今や企業が存続していくための欠かせない課題です。また、それは、サプライチェーン全体で考えていくべきテーマでもあります。今後もこのような機会を積極的に設け、熊谷組と熊栄協力会が密接に連携しながら、人権の取組みを前進させていきたいと考えています。
<塚田氏コメント>
安全管理についてしっかりした取組みが行われている。
それら人権への意識をサプライチェーン全体に広げていくべき。

今日、皆さんの意見を聞いていて、しっかりした意識を持って取り組んでいるという印象を受けました。なかでも人権において重要な分野である労働安全衛生については、建設業ということもあり進んだ取組みが行われています。
一方、課題としてあげられるのは、多重下請けによる問題点が指摘されていたように、サプライチェーン全体でいかに取組みを徹底していくかということ。もしもどこかで問題が発生すると、熊谷組や熊栄協力会に大きな影響が及びます。皆さんの企業における事案ではありませんが、外国人労働者に対する深刻な人権侵害事案も報道されており、そうした会社にはサプライチェーンから外れてもらうような考え方も時には必要だと思います。

もう一つは、建設会社にとって顧客となる発注元との関係です。サプライチェーン全体で処遇の改善を図っていくためには、発注元にも理解してもらい認識を変えていくことが欠かせません。私が携わっている他の業界でも、少しずつ変化が見られる発注元企業もあります。
このことは、熊谷組や熊栄協力会の皆さんの課題というよりは、日本社会全体の課題といえるでしょう。今日は貴重な意見が交わされたと感じています。熊谷組と熊栄協力会で問題意識を共有し、これからも一体となって人権の取組みを進めていってほしいと考えています。