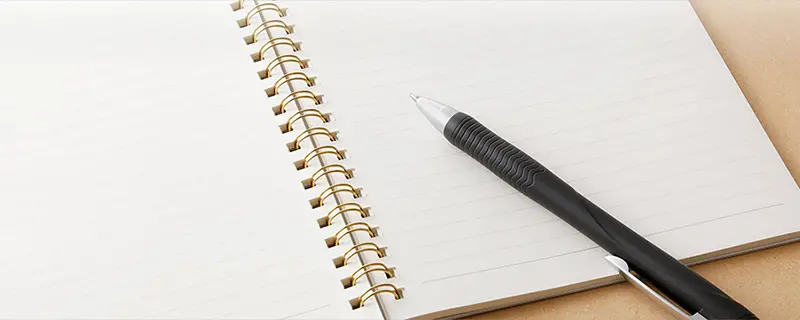温かい雰囲気と親身な対応が
入社の決め手
大学では建築学科を専攻していました。最初は建物の形やデザインといった「意匠」に興味があったのですが、勉強を進めていくうちに、そこで過ごす人々の快適さを生み出すシステム作りに面白さを感じるようになりました。そこで就職活動では、設備系の仕事を中心に募集を探していましたね。
そのなかでもゼネコンを志望したのは、学生時代から一人で黙々と作業するよりも、みんなで一つのことを成し遂げるというほうが好きだったこともあり、意匠設計や構造設計、施工、積算など幅広い分野の人と関わりながらひとつの建物を造り上げることに魅力を感じたからです。
就職活動中は、建設会社の設備電気設計職の募集をチェックしていたのですが、どの会社も業務内容の説明が少なく悩んでいたんです。そんなとき、熊谷組はエントリーシート提出後に設備社員との面談の機会を設けてくれました。面談では実際に建てた物件の写真を見せてもらいながら、正直に「大変なこともあるけれど、建物が完成したときの達成感はかけがえのないもの」という生の声を聞くことができました。
また「サポート体制も整っているから、安心してこの業界に進んで大丈夫」と、私の不安に寄り添った説明をしていただき、このような社員の方々の温かい雰囲気や親身な対応が、私が熊谷組に入社を決めた一番の理由です。

設備電気設計の仕事の肝は
“コミュニケーション”
設計職と聞くと、ひたすら作図をするイメージがあるかもしれません。しかし実際は、お客様から聞き出した要望を図面化するための条件整理や、設計監理と言われるような、現場で施工が問題なく進んでいるかを施工図や納入仕様書で確認することが主な業務です。
例えば、建物内の照明ひとつにしても、最適な明るさを確保する「利便性」と、お客様が要望する「意匠性」を両立させる必要があります。
そのため、発注者やメーカー、施工業者など多くの関係者とコミュニケーションをとりながら仕事を進めていくのが基本です。私がコミュニケーションをとる際に大切にしていることは、お客様から要望をいただいたら、すぐに現場と共有・相談することです。早い段階で情報を共有できれば、現場社員の持つ知恵を借りることができますし、自分一人で考え込んでいる間にも現場の作業は進んでいきますので、早めに相談することで現場の負担を減らし、施工をスムーズに進めることにもつながります。
また、熊谷組の社訓に『工事施工に当たりては親切を旨とし得意先の不安の除去に努められたし』とあるように、相手を気遣いながら仕事を進めることを心がけています。すべてのお客様が必ずしも電気設備に詳しいわけではありません。内容がわからないことは判断できないと思うので、相手の知識量に合わせて専門用語をできるだけ一般的な言葉に言い換えたり、図や写真を使って視覚的に伝えたりと、なるべくわかりやすく伝えられるよう説明の仕方を工夫しています。
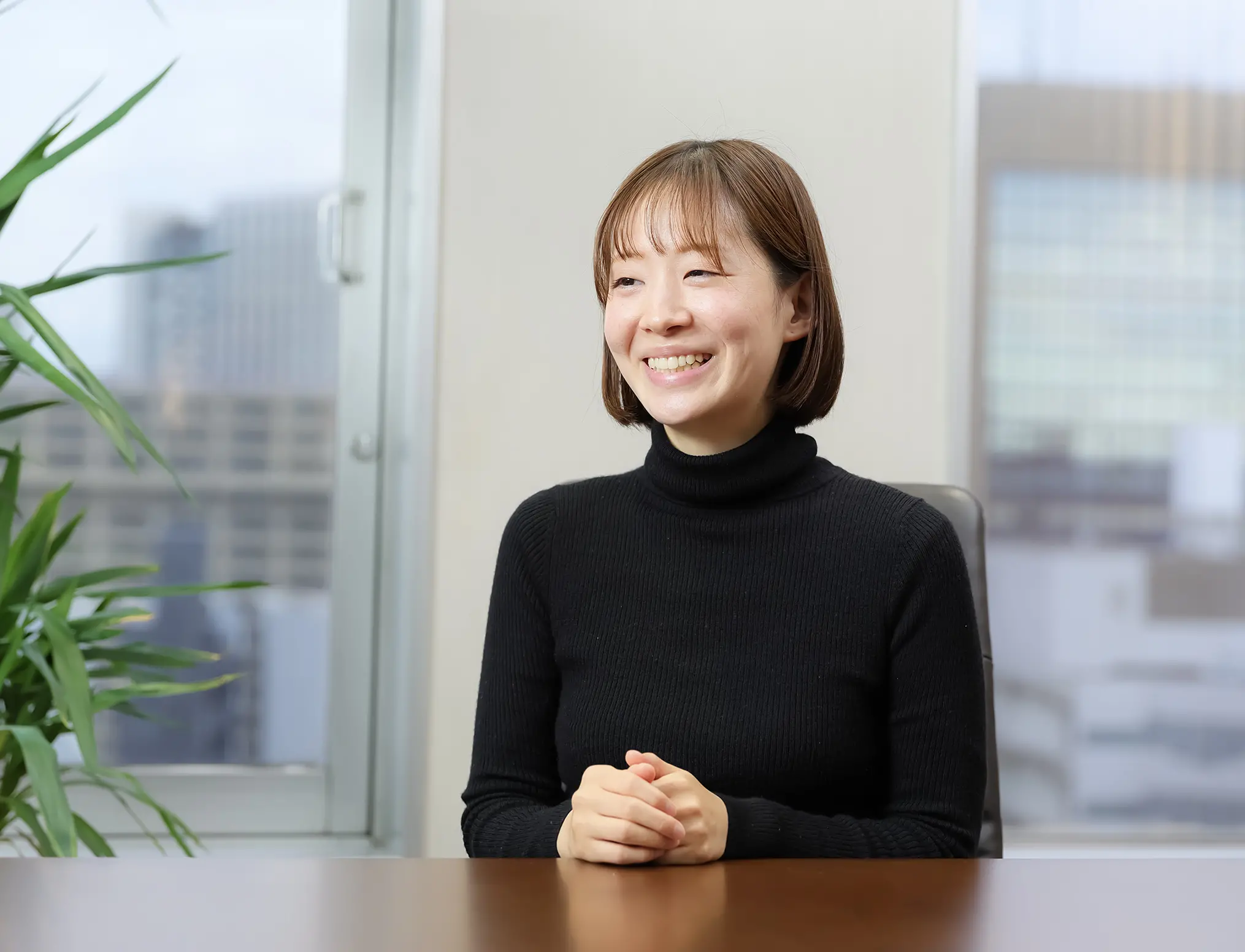
すべての物件に思い出が
詰まっている
設備電気設計の醍醐味は、建物を使う人に快適な空間を提供できることです。ただし、デザイン性と利便性の両立や、コスト面での理想と現実のギャップなど、さまざまな要素のバランスをとることが求められます。
性能の高いシステムを提案しても、お客様がその機能を使う場面がなかったり、月々の電気料金が高額になったりして、使い勝手の悪い建物になってしまっては意味がありません。建物の用途や使う人の生活をイメージしながら、イニシャルコストとランニングコストの最適なバランスも考えた設計を目指しています。
私が初めて主担当として設計から監理まで携わった物件は、高層の高齢者施設でした。その物件では着工後に照明計画の大幅な変更が必要になり、大変苦労した思い出があります。
高齢者施設では、明るめの照度設定が基本です。しかし、他の高齢者施設との差別化を図るために、照度を暗めにしてホテルを思わせる雰囲気を出したいという要望をいただきました。この相反する要求をどのように両立させるか悩みましたね。
工期が厳しいなか、 デザイン業者やメーカー、施工担当など物件に携わる多くの方々とコミュニケーションをとり、協力しながらひとつずつ課題を解決していくことで、無事に竣工を迎えることができました。竣工後、建物内の照明が一斉に点灯した瞬間は壮観さを感じると同時に、安堵の気持ちも溢れてきたことを覚えています。
設備電気設計担当として、竣工後にお客様から「明る過ぎず暗過ぎない、ちょうど良い明るさが実現できて満足です」というお言葉をもらえることもあり、その度にやりがいを感じますね。また、現場のみなさんからも「めげずに頑張ってくれたから、無事にできたよ。」というお声をいただくこともあり、その言葉もとても嬉しいです。
今でも担当した物件の近くを通ると、さまざまな思い出が蘇ります。別の物件では、お客様と一緒にスポットライトの角度を何度も調整して、最適な明かりを設定した経験もありました。物件ごとに用途も違えば携わる人も違うので、すべての建物に特別な思い入れがあります。

経験の幅を広げ、
後輩に熊谷組の技術を継承したい
これまでは主に高層のマンションや高齢者施設を担当してきましたが、最近は希望して工場や事務所ビルも担当し始めています。以前は物件の用途ごとに担当が分かれていましたが、今の熊谷組は垣根をなくす方針をとっています。これは、社員一人ひとりの経験の幅を広げ、技術力を高めていこうという取り組みの一環です。
物件の用途によって、設計上で気をつけるポイントは異なります。例えば工場では、製造品の特性に応じて防虫対策を講じなくてはいけませんし、最近では以前のように殺虫灯を使うのではなく、建物の外部に誘虫灯を設置して虫を建物内に入れないようにするなど、工場特有のチェックポイントがあります。
さまざまな物件を担当することで、自分自身の成長にもつながっていると感じています。これまでは自分が利用できない建物を担当することが多かったので、将来は商業施設やホテルも手がけてみたいですね。実際に利用してみて、使う人の視点で建物を見ることで、新たな気付きを得ることができると思います。
また、若手が働きやすい環境作りにも力を入れています。私自身、入社してから上司や先輩方から手厚いサポートをいただき、時には他愛もない話や悩みを聞いてもらいながら成長できました。今度は後輩が相談しやすい雰囲気を自分が作る番だと思っています。これまでは現場にいることも多かったのですが、時間があるときはなるべくデスクにいて、後輩が質問をしやすいような雰囲気作りを意識しています。
業務面では、設計図を作る際の標準図の改訂や、仕事で困ったときに確認できる資料をストックするフォルダの作成などを実施しました。このように、最近では熊谷組の技術を確実に若手に継承できる仕組み作りに取り組んでいます。
SCHEDULE
1日のスケジュール
朝
出社
現場定例資料の作成
施工図、納入仕様書のチェック
昼
休憩
移動
現場定例
顧客現場巡回に同行
現場分科会(総合図の確認、施工図のチェックバック等)
夕
現場から直帰

就職活動は、さまざまな業界を研究できる貴重な時間です。焦らず慎重に、自分の進みたい道を探してみてください。
設備電気職に少しでも興味がある方は、ぜひ熊谷組の会社説明会や面談にお越しください。実際に熊谷組の社員と話すことで会社の雰囲気や仕事への理解が深まり、入社後のギャップを減らせます。
私の部署では、お客様に積極的に要望を聞きに行く性格の人もいれば、お客様に最適な仕様を黙々と考える性格の人もいます。それぞれの持ち味を活かしながら、多くの人が活躍できる環境が整っています。また、早い段階から責任ある仕事を任せてもらえる社風があるので、着実に成長できる会社だと言えます。
ご縁あって入社された際には、熊谷組で一緒に協力しながら挑戦しましょう!
- 所属・役職・内容は取材当時のものです。