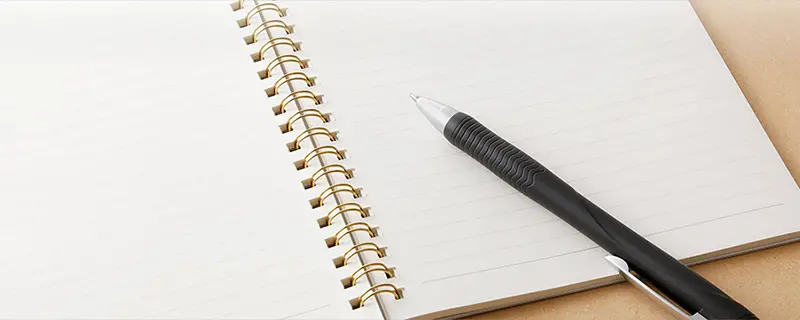現場で活躍する
機電職との出会いが決め手に
大学院時代、宇宙科学研究所(ISAS)で実験を行っていた際、敷地内の宇宙開発を行っている企業の展示ブースがあり、ゼネコンでも機械系が活躍できることを知りました。もともと航空宇宙系の道を志望していましたが、その後友人からのお誘いで熊谷組の現場見学に参加したことも重なって、ゼネコンへの就職を意識するようになりました。
熊谷組の現場見学では、機電職の方が第一線で活躍している姿を目の当たりにし、スケールの大きなものづくりに強く惹かれました。機械系出身でも歓迎してもらえる雰囲気があり、新たな可能性を感じたのも、志望した理由のひとつです。
面接時や見学時に感じた印象は入社後も変わることなく、さまざまなサポートを受けられる環境で日々スキルを磨いています。資料をまとめる力はもちろん、大学院で培った解析やプログラム系の知識も、今の仕事で役立っています。

"工事を止めない"責任と誇り
入社後最初に配属された埼玉県秩父の現場は、全長3キロメートルほどの小断面の水力発電導水路トンネル工事でした。入社2年目から4年目までの3年間、トンネル掘削の開始から完了まで携わり、機電職としてさまざまな経験を積めたと感じています。工事の後半では発注者から当初想定にない要望を受けることもありましたが、最初からあらゆる事態を想定して計画を立てていたおかげで、追加対応もなく工期と予算内で対処できました。
トンネル工事の経験を通じて実感したのは、機電職は現場をつなぐ重要な役割を担っているということです。現場では、電気や流体力学の技術的な知識はもちろん、コミュニケーション能力も必要不可欠だと常に感じています。他愛もない会話でも、関係性が深まることで仕事がよりスムーズに進められるようになるので、現場の方との何気ない会話から信頼関係を築き、業務を円滑に進められるよう心がけています。
日々の業務の中で、とくに大切にしているのは、工事を止めないこと。工事が止まることで、機械のリース代や作業員の方の人件費など、さまざまなコストが発生してしまいます。そのため、不具合が発生したら、仮復旧を行い、なによりもまず工事を継続できる状態にすることを最優先に考えています。
機械系の知識は、トンネルの掘削機械のメンテナンスでも活きています。機械が故障した時には、油圧系統や電装系の知識を活かして迅速に対応できます。

"1人"じゃない、
チーム熊谷組の強み
機電職は、すべての現場に必ずしも常駐するわけではありません。現場の必要に応じて配置が決まり、多いところでは4人体制のこともあります。
私の場合は、これまで2つの現場を1人で担当してきましたが、心細く感じることはありませんでした。右も左も分からない初めての現場でも、本社の上司が頻繁に連絡をくれ、つまずいた点について丁寧に教えてくれたことで、電源設備の計画なども、手厚いサポートのもとで1人でも進めることができました。また、電気設備について専門業者の方に相談をさせてもらったり、機械トラブルがあった際には不明点を親身なって対応してもらったりと、熊谷組の上司だけでなく、業者の方々にも助けていただきながら、さまざまな課題を解決していったことも覚えています。
竣工後に発生する機械や電気設備のトラブルに対しては、迅速な対応が求められます。そのため、知識やスキルの習得も欠かせません。そうした社員個人が蓄積したノウハウやナレッジを共有し、組織全体の業務効率化を図る取り組みとして、機電職の社員が集まり、技術開発の状況や現場の課題を共有する「機電技術会」を実施しています。
東ブロック・西ブロックに分かれての地域ごとの集まりと、全国での集まりが年2回開催されますが、「こういうことで困っているんだ」と相談すると、先輩方からすぐにアドバイスをもらえるので、現場力向上につながる学びの場になっています。

宇宙開発への夢を追い続けて
熊谷組に興味を持ったきっかけは宇宙開発分野の学問に、自分が携わっていたことでしたし、大学院時代に宇宙科学研究所で実験を行っていた経験もあるので、将来は熊谷組の宇宙開発プロジェクトにも携わってみたいですね。
今は目の前の現場で、機電職としての専門性を高めることに注力しています。現場のプロフェッショナルとして、機械や電気設備のエキスパートになることが目標です。これまでは上司のサポートを受けながら仮設備を設置してきましたが、仮設備の計画から稼働まですべて自分一人でできるような一流の技術者になりたいと考えています。
「トンネルの熊さん」として、これからも難所難物を形にして、社会に貢献していきたいです。さまざまな視点からものを考えられる、独自の現場力を持った技術者を目指して、日々精進していきます。
SCHEDULE
1日のスケジュール
朝
朝礼
仮設備点検、仮設備不具合対応
昼
翌日の作業打ち合わせ、休憩
夕
仮設備計画、作業計画書作成
退社

機械系学部の学生の皆さんは、メーカーへの就職を考える方が多いかもしれません。しかし、ゼネコンも魅力的な進路のひとつなので、ぜひ選択肢に入れてもらいたいと思います。
熊谷組の機電職は若手でも存分に活躍し、成長できる土壌があります。機電職は全国転勤がありますが、それも魅力のひとつです。行く先々の土地の良さを知れるので、働きながら旅行しているような気分にもなります。私自身、秩父で過ごした3年間では、日本三大曳山祭のひとつである秩父夜祭に行くなど、その土地ならではの貴重な経験ができました。知らない土地に住むことが好きな人には向いている仕事だと思います。
私が携わっているトンネルを築造するプロジェクトでは、シールドマシンなどの掘削機械が活躍しています。これらの機械設備を安定して稼働させる機電職は、建設現場にはなくてはならない存在だと言えるでしょう。
万が一、トンネルの掘削機械が壊れた時には、油圧や電装品の知識が必要になるので、機械・電気分野を専攻した人なら、学んだ知識を生かせる場面があるので安心してください。
機電のスペシャリストとして現場の第一線で活躍できる環境で、一緒に挑戦してみませんか。
- 所属・役職・内容は取材当時のものです。